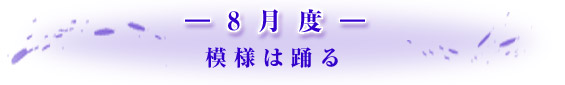ギャラリー 2009年 8月度
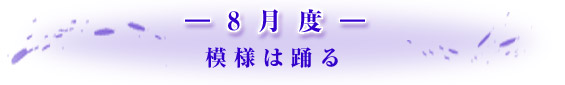
ものを盛るなら邪魔にならないように 飾ることが目的なら目一杯美しく…
器の模様は、作り手によって考え方 表現の仕方も様々です。
彫ったり 筆で描いたり 色を差したり、
造形以上に作者の個性が直に強く表われるのが陶芸の絵文様です。

旭 栄彰「染付皿」
径22.0×2.0cm

岡田よし子「色絵山茶花図飾皿」
径22.0×2.0cm

大竹 栄「色絵野菜尽文皿」
径22.0×2.0cm
既製の磁土の皿を用いた三人三様の作品をご紹介します。
左は、呉須で描き 石灰透明釉を掛け還元焔焼成した染付絵皿。呉須の濃淡も程よく 丹念に描き込まれた海の生物は、生き生きと皿に配置されています。
中央は、皿を下絵付なしで焼いた白無地に低下度焼成の上絵付で山茶花を描いています。
右は、染付本焼後に上絵付で赤と黄・緑で彩色。高度な表現技法 色鍋島の写しです。

出光昭介「釉彩花文皿」径21.5×高6.0cm
高火度焼成の色釉を使っても彩り豊かな絵文様が描けます。当倶楽部では釉彩と呼んでいます。
下絵顔料 弁柄での輪郭があるかないかで雰囲気が違ってきます。

竹谷嘉彦「釉彩花文皿」 径25.0×2.0cm
同じ釉彩花文様も 艶黒釉のバックが花をより浮き立たせています。丹念な筆置きで、
皿全面を色釉で覆い尽くしています。

黒木登志夫「黒掻落魚文皿」
径21.5×高3.0cm
化粧土を活かして模様を入れる技法のひとつが「掻落し」です。生素地に黒化粧で魚形を描き、掻落し文様を入れ、素焼後 青白釉を掛け、酸化焔焼成しています。
カップは土の色で文様を作る練込技法。色土と白土を重ねた縞模様、さらにひと手加えて鶉手に。
タンブラーは素焼後 市販の陶器用クレヨンで紙に描くように塗り分け透明釉を。口辺から内側には織部釉。

前 大橋清子「練込カップ」
径7.0×高8.0cm
奥 田向章子「クレヨン描タンブラー」
径8.0×高13.0cm

間宮英子「貯金箱 猫」縦16.0×横15.0×高27.0cm
小作陽子「お地蔵様」径6.5×高12.0cm
今にも動き出しそうな猫の陶彫。体に花模様を粘土で貼り付け 色をのせ、お洒落しています。
お地蔵様が羽織っている着物の柄は 黒化粧象嵌文。黒化粧が白マット釉に反応し 弁柄のように発色しています。
線象嵌文様はきめ細かい白い土に施すことで、繊細かつ明確に表現できます。墨呉須と焼貫呉須を使い分けて象嵌し、色釉で彩りをそえ、明るく楽しい絵柄の蕎麦猪口になりました。

安倍眞理子「呉須象嵌蕎麦猪口」径9.0×高7.0cm
ミニギャラリー情報
日比谷ミニギャラリー
このページで紹介している作品をはじめ 当倶楽部会員の制作した作品を 毎月入れ替え展示しています。
- 場所:
- 地下鉄 日比谷駅 A5出口 階段途中
東京都千代田区有楽町1-5-2 東宝ツインタワービル